AIがどうのという広告一気に増えましたね!
「AIが流行っているから」「競合が取り入れているから」…そんな理由でAIを導入しようとしていませんか?
現場で多くの経営者と話すたびに感じるのは、「AIを入れれば何かが変わる」という幻想が、思いのほか根強いことです。
しかし、AIは魔法の道具ではありません。
何を変えたいのか、どこを改善したいのかを決めずに導入しても、結局は高価な箱モノになってしまうのが現実です。
今回のコラムでは、「AIで何を変えたいか」を明確にする重要性と、そのために経営者自身が考えるべきポイントをお伝えします。

1.なぜAIを入れたい病が起きるのか?
「AIを入れないと、なんだか遅れてしまう気がする!」
「他の会社も使い始めたらしいし、うちも何かやらなきゃ…」
そんな声を、経営者の方からよく耳にします。
テレビやネットの広告でも「AIで売上アップ」とか「人件費が削減できる」なんて話がたくさん流れてくるので、つい焦ってしまうのも無理はありません。
でも実際には、「何を変えたいのか」が決まらないままAIを入れようとしている会社さんが、とても多いんです。
現場で「AIやりたいんだけど…」という相談を受けることが多いのですが、話を深掘りすると、具体的にやりたいことがまだ見えていない場合がほとんどなんですよね。
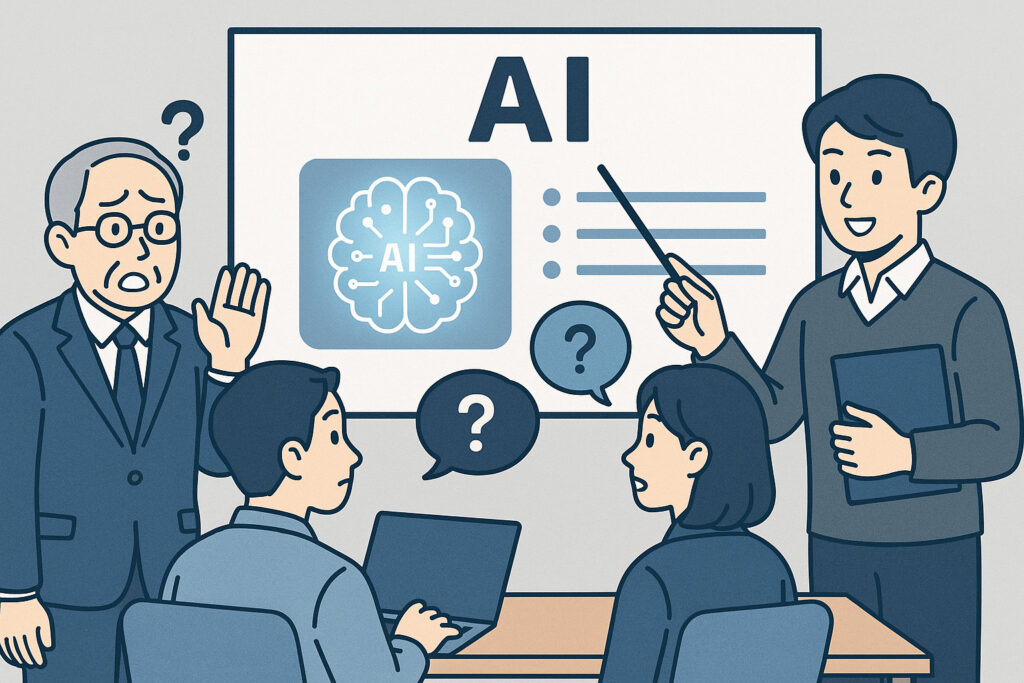
ある会社でAI会議が始まった!
ちょっと前にこんなことがあったんですよ。(一応ここまで書いてOKいただいてます)
ある会社で「AIを導入するぞ!」っていう話になって、社長が社内に「AIプロジェクトチーム」を立ち上げたんです。
で、記念すべき第1回の「AI会議」が開かれたんですけど、これがまあ、大変で…。
会議室には社長をはじめ、営業、事務、そしてシステム担当のエンジニアさんが勢ぞろい。私もオブザーバー的に発言なしで参加していました。
ところが会議が始まった途端、エンジニアさんが延々と話し始めたんですよ。
「ChatGPTはニューラルネットワーク理論が…」
「パラメータが数兆単位で…」
「推論と学習は別でして…」
みたいな感じで、AIの仕組みの説明が止まらない。
社員さんたちは最初は頑張って聞いていたんですけど、だんだん表情が固まってきて、メモを取る手も止まり…。寝てしまう人も。
気が付いたら、社長まで腕を組んで「うーん」と唸ってる。
結局、エンジニアさんが1時間も技術の話を続けた末に、誰かがポツリと
「で…結局、ウチでAI入れて、何が変わるんですか?」
って聞いたんです。
そしたらまたエンジニアさんが「うーん、それはですね…」って技術の話に戻ってしまい。
結局、その日の会議は「AIってすごいけど、ウチでは何に使うんだろうね?」って、全員が首をかしげたまま終わっちゃったんです。
エンジニアさんがOpenAIやGoogleのガチ開発者でAI自体を作った人であればこういう話でいいんですが、
社内のエンジニアさんもその開発者から見たら「ユーザー」でしかありません。ワタシも含め全員が「ユーザー」です。
なので、そういうことはAIに聞くか、ググればいいし、AIに詳しい人のYouTubeをそれぞれ観ればいいと思います。
それよりも
AIを入れる前に、一番大事なのは「何を変えたいか」を決めること
仕組みの話ももちろん大事ですけど、それ以前に「会社のどの部分を変えたいのか」が決まらないと、AIはただの「ちょっと先に使った人の知識自慢大会」で終わっちゃうんですよね。そうならないように「社内の課題って何だろう?」「社内の課題をAIを使って解決できないか?」というアプローチの会議にすると、皆さんの貴重な時間を奪わなくなります!
2.経営者がAI導入で一番やってはいけないこと
①「社員に任せる」「若い子にやらせる」は危険
②経営者自身が課題を言語化しない限りAIは役立たない
③AIは魔法ではなく「課題解決のツール」に過ぎない
①「社員に任せる」「若い子にやらせる」は危険
「AIのことは若い子の方が詳しいから、任せとけばいいよ」
そんなふうに言う社長さん、実はすごく多いです。
でも、これはかなり危険なんですよね。
若い社員さんは確かにSNSやスマホには強いかもしれないけれど、会社の全体像や経営の課題までは分からないことが普通です。
「AIを使って何を変えたいのか」というビジョンを社長自身が持たないまま任せちゃうと、AIは結局、「画像や文章を生成しておしまい」といったような手段だけになって
おもちゃで終わってしまうことが多いんです。
経営におけるAIは、経営者が舵を取ってこそ活きるツールなんです。
②経営者自身が課題を言語化しない限りAIは役立たない
よく「AIで何かできないかな?」って言う経営者の方がいますが、これが一番の落とし穴なんです。
AIは「何を解決したいのか」がはっきりしていないと、力を発揮できません。
例えば「残業を減らしたい」なら、どの業務に一番時間がかかっているのか。
「売上を伸ばしたい」なら、どこのお客さんを狙いたいのか。
課題を具体的な言葉にするのは、経営者にしかできない仕事なんです。
ここを飛ばしてAIを入れても、まず上手くいかないんですよね。
③AIは魔法ではなく「課題解決のツール」に過ぎない
世の中では「AIで売上10倍!」とか、「人件費ゼロ!」みたいな派手な話がよく流れていますよね。
でも現実は、AIは魔法の杖じゃないんです。
AIはあくまで「課題を解決するための道具」に過ぎなくて、勝手に経営の悩みを解決してくれるわけじゃないんですよね。
経営者自身が「何を変えたいのか」を考えて、そこにAIを使うからこそ意味が出てきます。
「とりあえずAIを入れれば何とかなる」と思っていると、時間もお金もムダになってしまうんです。
3.行政の補助金がAIと言っていても結局IoTだったりする
実は、これもよくある話なんですが、行政の補助金の説明会なんかで「AI導入を支援します!」って大きなタイトルが掲げられているのを見かけるんですよね。
「おっ、いよいよ行政もAIに本腰入れるのか!」と期待して中身を聞いてみると、だいたい半分以上がIoTの話だったりするんです。
例えば「センサーを工場に取り付けてデータを集めましょう」とか、「温度や稼働状況を遠隔でモニタリングしましょう」とか。
もちろん、それ自体はすごく大事だし、立派なDXなんですけど、それはIoTであって、AIそのものじゃないんですよね。
IoTは、あくまでもデータを集める「仕組み」です。
そこから先、「集めたデータを分析して未来を予測する」とか、「文章を書いてくれる」とか、そういう部分がAIの領域なんです。
IoTが「目や耳」みたいな役割なら、AIは「脳」みたいな役割。
でも行政の補助金や支援策では、AIとIoTがごちゃごちゃに語られることが本当に多いんです。
そのせいで、経営者の方たちが「ウチもAI導入しよう!」と思って補助金の説明を聞きに行ったら、
「え…それって工場にセンサー付ける話?ウチはサービス業だから補助対象外だよね。」
みたいに拍子抜けすることもよくあります。
しかも、IoTって導入コストもかかるし、結局「専用機械を買ってください」(銀行から融資してください)ありきの補助金に業種によってはそもそも必要ない場合もありますから、経営者としては「ウチには関係ないかな…」って思ってしまうんですよね。
北海道は第一次産業や工場なども多く、もちろんIoTとAIのハイブリッドは重要です。ただ、そういう「ハード面」にばかりに予算が使われてしまって、経済をよくする部分の多くの「ソフト面」の中小企業さんが導入していくハードルがいきなり高いものになってしまいます。
本当はAIって、もっと身近で、小さなことから使い始められるんですけど。
補助金に踊らされる前に、まずは「自分たちが何を変えたいのか」をしっかり決めてから考えましょう、といつもお伝えしています。
というわけで
今日は「AIを使う前に、何を変えたいか決めていますか?」というお話をしてきました。
AIは確かにすごい技術ですし、これからの時代に避けて通れない存在だと思います。
でも、AIそのものが目的になってしまうと、結局はお金と時間のムダになってしまうんですよね。
「若い社員に任せればいいや」も危険だし、行政の補助金だからと飛びついてみたら、ただのIoTの話で終わってしまうこともあります。
大事なのは、やっぱり経営者自身が「ウチはこれを変えたい」「ここを効率化したい」というゴールを決めること。
そこが決まっていれば、AIは本当に強い味方になってくれます。
AIは魔法じゃありません。だけど、使い方次第で未来を変えるツールにはなる。
もし「何から考えたらいいか分からない」という方は、ぜひ一緒にAIで整理していきましょう!!